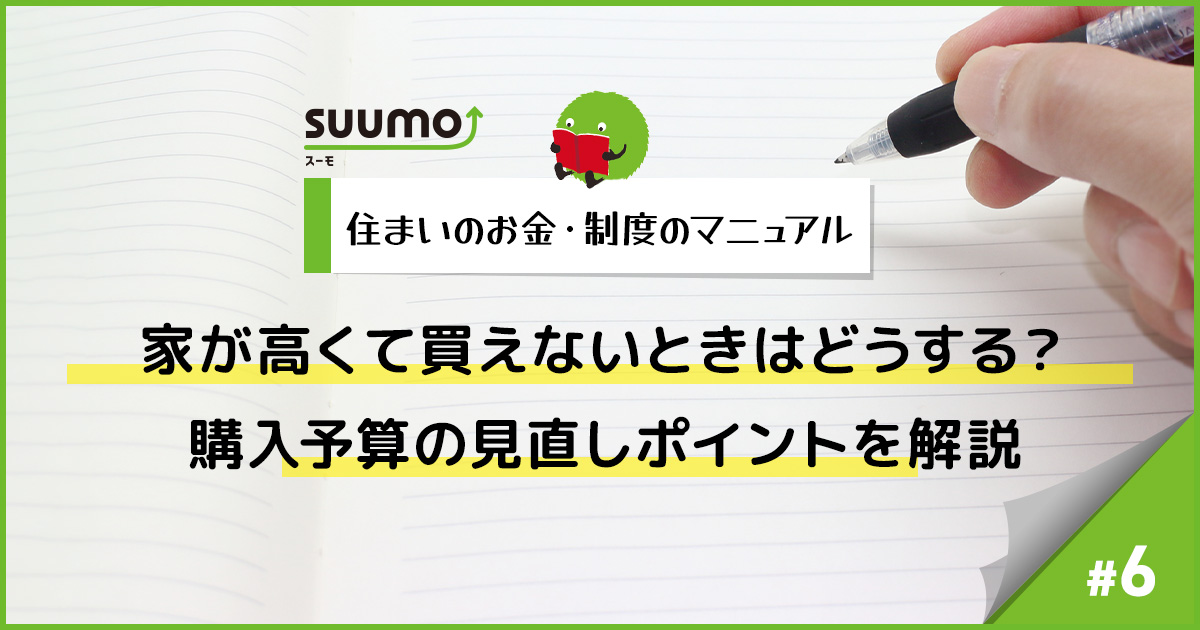
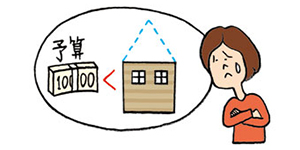
「気に入った家が見つかったけど、購入予算より価格が数百万円高い…」。そんなとき、何とか予算を上げる方法はないものか? 将来の家計も考えた上で「予算アップ」する方法をアドバイスしよう。
予算アップの方法として最初に思いつくのは住宅ローン借入額の増額だが、返済額が増えて家計に負担がかかることも。そんなときは、親に「住宅資金」の援助を頼むのも一つの方法だ。マイホームの購入や新築、増改築をするための費用を親や祖父母等からもらう場合、贈与額500万円まで贈与税がかからない制度が利用できる(※)。贈与税の基礎控除額110万円と合わせ、610万円の贈与までは贈与税がかからないのだ。
→詳しくは…住宅取得等資金贈与の非課税の特例
※最大500万円の贈与額まで非課税になるのは、一般的な住宅を取得する場合。省エネ性能・耐震性能・バリアフリー性能のいずれかが一定基準以上の住宅の場合、最大1000万円の贈与額まで非課税となる(2023年12月31日までの住宅取得が対象で、適用には一定の条件がある)
「親から大金を援助してもらうのはどうも……」という人は、親からお金を「借りる」方法もある。ただしこの場合、無利息での借り入れや「あるとき払い」の返済では、贈与とみなされ贈与税がかかることも。借入条件をきちんと決めて借用書を交わし、定期的に返済することが大切だ。
家計を見直して毎月返済額を1万円増やせれば、借入額を約340万円増額できる(金利1.2%、35年返済の場合)。家計を見直し、普段何気なく払っているお金は本当に必要なものなのか、じっくり見直してみよう。特に節約効果が高いのは保険料や通信費だといわれている。
(1)生命保険料
生命保険の保険金額を万が一の場合の「住居費」も考えて決めているなら、その分減額できないか検討しよう。住宅ローンを借りて家を買うと、契約者の死亡や高度障害時にローン返済が免除される団体信用生命保険に入るケースが多く、住居費分はこの保険でカバーできるからだ。なお、契約変更の手続きは家の引き渡し後に行おう。
(2)通信費など
携帯電話の料金プランや、インターネットのプロバイダー契約の内容など、無駄がないか細かくチェックしてみよう。新聞や定期的に購読している雑誌なども、本当に必要なのか、また、もっと安く済む方法はないか、この機に見直してみよう。
(3)マイカー
車を手放せば、駐車場代やガソリン代、自動車保険料など、毎月数万円単位の節約が可能。最近は、気軽に車を借りられるシステムもあるので、車を持つ場合と必要な時に借りる場合の費用をシミュレーションしてみよう。
(4)嗜好品、外食費など
自動販売機やコンビニで購入するペットボトル飲料やタバコなどの嗜好品や、週末ショッピングで使ってしまうお金など、日常の何気ない支出が毎月いくらになるのか一度チェックしてみよう。例えば、1日1本の缶コーヒーをやめてマイボトル持参にするなど、節約できるポイントが見つかる可能性が高い。
住宅ローンは年2回、ボーナス月などに返済額を増やすことができる。一般的に「ボーナス時加算」「ボーナス返済」と呼ばれる方法だ。例えば、ボーナス時加算額を5万円に設定すると借入額を約285万円増やせる(金利1.2%、35年返済の場合)。ただし、ボーナスの支給額は景気や会社の業績に左右されやすいので、ボーナス時加算額を多くしすぎるのは危険。ボーナスは最低の場合いくら程度になるのか会社の給与制度などを調べ、その場合でも余裕をもって返済できる金額にしておこう。
共働き夫婦の場合、将来妻が退職する可能性を考え、夫1人の収入で返せる分だけ借りるケースが多い。ただ、その借入額では欲しい家にあとちょっと手が届かないという場合、妻も住宅ローンを借りて予算アップする方法もある。ただし、将来子どもの誕生などで夫婦のどちらかが時短勤務を選択したり退職したりする可能性が高いなら、10年程度で完済可能な借入額にしておこう。
新築マンションのなかには、引き渡しまでの期間が1年以上の物件もある。こういった物件なら、引き渡しまでの間に節約を重ね、住宅資金を増やすのも一つの手。例えば、引き渡しまで親の家に同居させてもらって家賃を節約する、妻も働いて収入を増やす、車を手放すなど、期間限定で資金を増やす工夫をしよう。なおこの場合、売買契約時点は住宅ローン借入額を多めにし、引き渡しの約1カ月前に行われる住宅ローン契約時に、借入額を減らす手続きをすることになる。もし、それまでに貯められない場合、借入額は減らせないので注意しよう。
気に入った家にどうしても手が届かない場合、予算に合わせて家の条件を変えるか、または数年計画で貯蓄をしてから家選びを再スタートするか、どちらかの選択になる。後者の場合は、何年でいくら貯めるか具体的な目標を立て、貯蓄先は金利が低くても着実に貯められる定期預金や財形貯蓄などにしておこう。また、家を買う年齢が高くなると、ローン返済が老後の負担にならないように返済期間を短めにすることも考えなくてはならず、その分借入額が減るケースも多い。貯蓄計画を立てるときはその点も考えておこう。
