改築や増改築、改修、リフォームなど、住宅の工事に使われる言葉の定義や違いを知っていますか?今回は、一級建築士の佐川旭さんに取材。改築とは何か、確認申請は必要なのかなど、知っておきたい知識をまとめました。
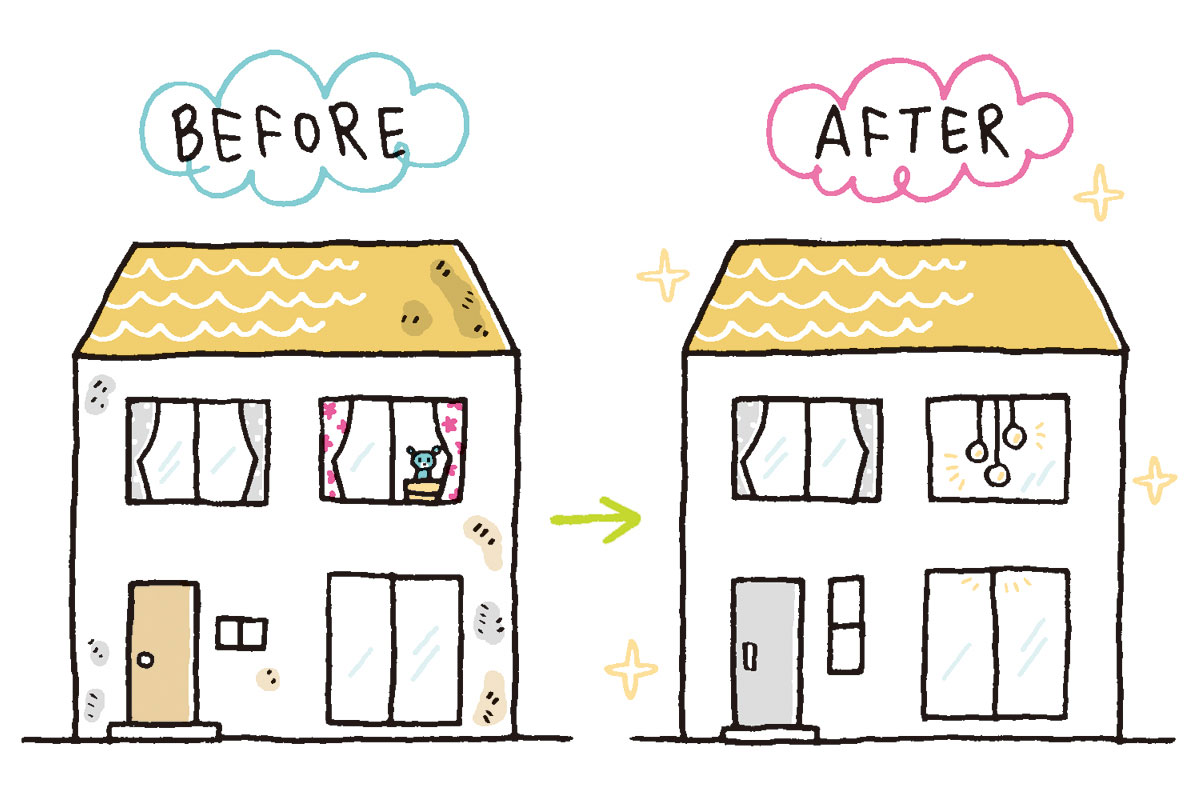
記事の目次
改築とはどんな工事?改修やリフォームなどよく似た言葉をおさらい
一戸建ての改築の定義は?
家のリフォームや増築をする際、「改築する」という言い方をよく耳にします。実は、「改築」は法律でその意味が定められていて、すべてのリフォームが改築というわけではありませんし、増築も改築とは別のものです。
改築の定義を定めているのは建築基準法第2条第1項第十三号。建物の一部、またはすべてを壊して、ほとんど同じような建物をつくり直すことを言います。
「改築は、もとの建物と規模が変わらないこと、構造部分に工事が行われることが特徴です。基礎を変更しないため、敷地に対する建物の位置は変わりません。建物の用途も変更しないのが改築なので、住宅の場合は改築後も住宅として使用します。構造も木造住宅を改築する場合は、木造で改築を行います。2階建ての住宅は2階建てのままです。ただし、モルタルの外壁をサイディングに変更するなど、外観の見た目が変わるのは、改築の定義に当てはまるかどうかの判断基準には含まれません」(佐川さん、以下同)

新築、増築、改修。それぞれの意味は?
建築基準法では、「建築」について「新築」「増築」「改築」「移転」の4つの定義があり、それぞれ以下のような意味になっています。
建築基準法での定義
新築
建築物のない土地に、新たに建築物を建築すること
増築
既存の建築物に建て増しをすること。または、既存建築物のある敷地に新たに建築すること
改築
建築物の全部または一部を除去した場合、または災害などにより失った場合に、これらの建築物または建築物の部分を、従前と同様の用途・構造・規模のものに建て替えること
移転
同一敷地内で建築物を移動すること。
(なお、2015年の建築基準法の改正によって、特定行政庁が認めた場合は敷地外への移転も移転の定義に含まれるケースがある)
では、改修はどのような工事をいうのでしょうか。改築とはどこが違うのでしょうか?
「改修についての法的な定義はなく、一般的には修理や修繕、間取り変更、住宅設備交換など、リフォームと同じような意味で使われています。ただし、リフォームよりも改修という言葉を使う場合は規模が大きめなイメージです。構造部分は壊さないという点で、建物の構造部分の工事を行う改築工事とは異なります」
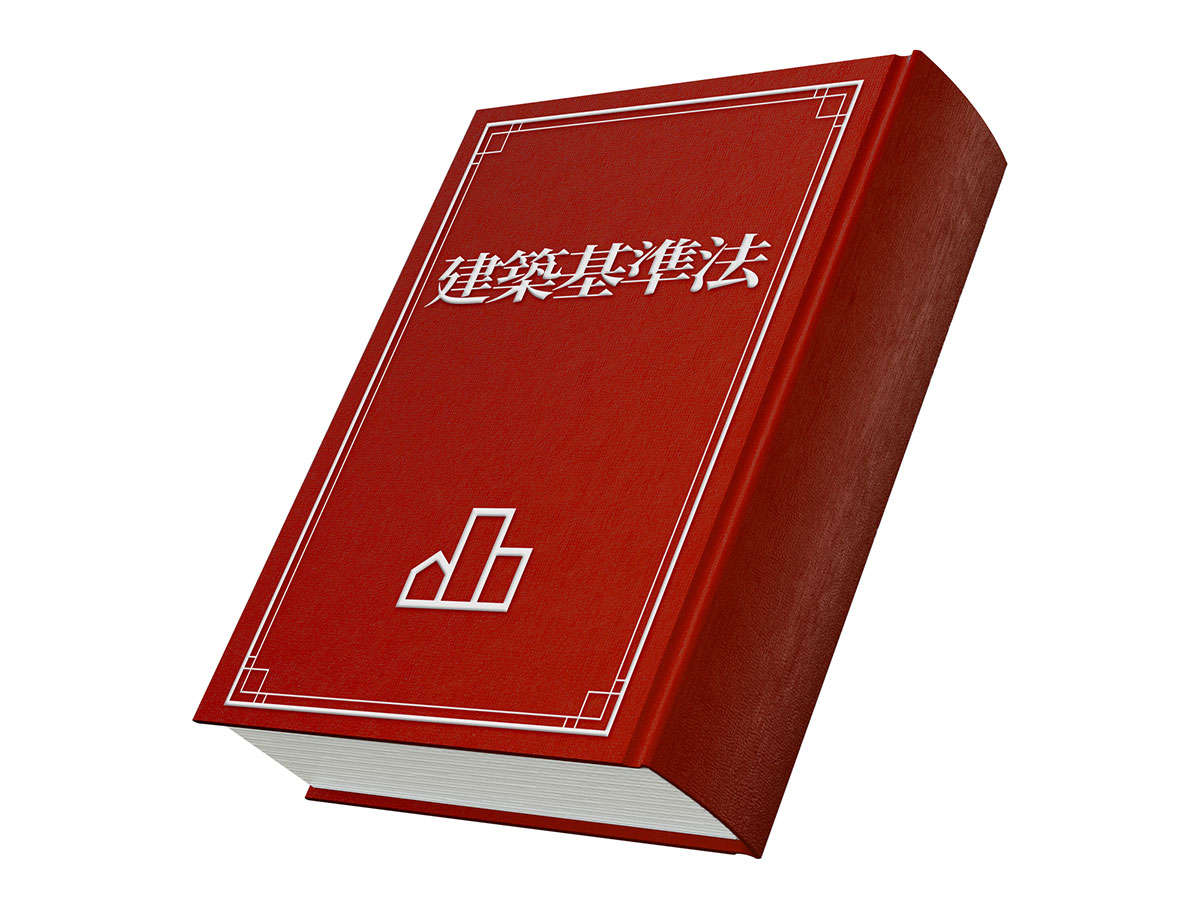
改築をするのはどんな場合?
改築はリフォームや新築に比べてコストがかかる
リフォームでは住宅設備を交換したり、構造を壊さない範囲での間取り変更をしたりで、建築基準法でいう「改築」の規模にはならないケースが多いそう。
「改築は、建物を壊し、撤去するための手間とコストがかかります。壊すための仮設工事も必要です。そのため、建物を壊さないリフォームや、解体や撤去が不要な新築に比べると、改築はどうしてもコストが高くなるのです」
吹抜けをふさぐ、つくる改築のケース
一般的なリフォームよりもコストがかかる改築を、あえて行うのはどのようなケースなのでしょうか?
「きっかけの一つは吹抜けの変更です」
例えば、吹抜けのある大空間のリビングで暮らしてきたけれど、かかりすぎる光熱費をどうにかしたい、2階の面積を増やして書斎や収納を増やしたいなどの理由で、吹抜けをふさぐ場合。家の規模や用途などは変更せず、構造を工事する改築のケースとなります。
逆に、子どもたちが独立して部屋数をもてあましたため、2階の床面積を減らして1階の玄関ホールやLDKに吹抜けを設けるケースもあります。

階段の位置や形状を変更するケース
「階段の位置変更も構造部分の工事が伴います。玄関近くにあった階段をリビング階段に変更したり、急な階段を緩やかにしたりするため、位置を変更するケースも改築にあたります」
リビングを広い空間に広げるケース
リビングの隣にある和室や寝室、子ども部屋を、家族構成やライフスタイルの変化であまり使わなくなることも多いでしょう。リビングを広々とした空間にするために、壁を撤去して隣接する使わない部屋と一体化する場合、新しく柱を加えたり、梁(はり)を補強するために一部鉄骨を入れたりすることがあります。この場合も、改築に当てはまります。
改築工事をする前に施主が知っておきたいことは?
工期がどれくらいの長さかを早めに確認
建物の解体や間取り変更など、大がかりな工事になる改築工事。工事中は普段通りの生活は送れなくなりますから、どうしてもストレスがたまります。どんなことがストレスになるかを事前に知っておくだけでも、負担は違ってきます。
工事の依頼先を決めたら、プランを検討する段階で早めに確認しておきたいのが着工から引き渡しまでどれくらいの日数がかかりそうかということ。
「改築の場合、3〜4カ月くらいかかるのが一般的。住みながらの改築工事は、ホコリや音で家族やペットのイライラがつのります」
長期にわたる工事になりそうなら、近くの賃貸アパートを借りて一時的に引っ越す方法もあります。ただし、着工直前に仮住まい探しを始めると、広さや立地が希望に合う物件が見つけられないことも。ペットがいる場合は、賃貸物件でペット可なところを見つけるのに苦労するケースもあります。
早めの工期確認と、仮住まいをするなら早めの物件探しが重要です。

近隣への配慮を忘れずに
車や人の出入り、資材の搬入や、廃棄物の搬出、工事による音やホコリなど、改築工事は近隣の人々にもストレスがかかります。近隣への負担を抑えるための配慮を、リフォーム会社、建築会社と一緒に考えながら工事を進めていく必要があります。また、工事がいつ始まっていつまで続くのか分からないことも近隣のストレスになり、トラブルに発展するケースも。改築工事の現場に工期を記載した看板を掲示しておくほか、事前にご近所にお知らせをしておきましょう。完成後も、近隣の方々とは長いおつきあいが続きますから、着工前、工事中の配慮が大切です。
耐震補強や断熱対策も同時にするとおトク
せっかく改築工事を行うなら、耐震補強工事や断熱対策も同時にするのがおすすめです。どちらも、工事の際に壁や床、天井などを解体・撤去するケースが多いため、一度に施工する方がコストダウンが可能です。
「職人さんの人件費だけでなく、交通費など細かな経費も削ることができるので、同時の施工が効率的です」
今のライフスタイルに合わせた間取り変更など、暮らしやすさを向上させる改築工事。耐震性や断熱性のアップでより快適にすることができます。
改築工事をすると建築確認申請は必要?
建物の新築や大規模な修繕の際に必要な手続き
建築確認申請とは、建物を新しく建てるときや、大規模な修繕をする際に必要な手続きです。リフォームの場合、木造2階建てで増築を伴わないのであれば申請は不要です。増築をする場合は、立地と増築面積によって申請が必要か不要かが決まります。防火・準防火地域で床面積が増えるリフォームをするなら建築確認申請が必要ですが、防火・準防火地域以外なら10m2以下の増築なら申請は不要です。
| 増築をする住宅の立地 | 建築確認申請 |
|---|---|
| 防火・準防火地域 | 増築面積にかかわらず申請が必要 |
| 防火・準防火地域以外 | 増築面積が10m2超なら申請が必要 |
改築は、基本的には建築確認申請不要
基本的に、改築の場合は建築確認申請は不要です。
「ただし、改築工事で柱や壁など主要構造部分の半分以上を変更すると、自治体によっては建築確認申請が必要になる場合があリます。対応が自治体によって異なるため、施工前に、改築後の図面を持参して、市や町の建築指導課に相談に行ってみるといいでしょう。実施する改築工事が受けられる補助金はないかなど、有益な情報を収集する機会にもなります」
建築確認申請は誰がするの?
もしも、建築確認申請が必要な改築工事と判断された場合、その申請は誰が行うのでしょうか?
「建築確認申請の申請者は施主、つまり、家を改築する人です。しかし、図面の手配など専門的な知識がない場合は自分で申請するのは難しいですから、建築会社やリフォーム会社の建築士に代行してもらうのが一般的です」

改築工事をすると固定資産税は上がる?
固定資産税が上がるのはどんなとき?
固定資産税とは土地や建物など「固定資産」とされる資産や、償却資産などに対してかかる税金(地方税)のこと。増築をすると固定資産税評価額が上がるため、税額は増えます。また、リフォームによって住宅の機能性やグレードが向上した場合も固定資産税が上がる場合があります。
改築工事での固定資産税アップは自治体による
改築の場合も、工事の規模が大きく、改築の結果、家のグレードが上がれば固定資産税評価額が上がり、固定資産税の税額もアップする可能性があるかもしれません。対応は自治体によって異なります。
改築工事で利用できる減税制度はある?
住宅ローンを利用した改築工事で所得税が戻ってくる
ローンを利用して改築工事をした場合は、要件を満たしていれば住宅ローン控除(住宅ローン減税)の対象になり所得税が控除されます。リフォームの場合、入居した年から10年間、年末のローン残高の0.7%が所得税から控除される制度。所得税から控除しきれなかった分は住民税から一部控除されます。改築工事を行って入居した翌年に、確定申告をする必要があります(会社員の場合、2年目以降は勤務先の年末調整で手続きが行われるため確定申告は不要)。
住宅ローンを利用して改築工事を行うのであれば、下記の要件に当てはまるかチェックしておきましょう。
- 対象となるリフォーム工事費用から補助金などの額を控除した後の金額が100万円超
- 店舗や事務所などの併用住宅の場合、居住部分の工事費がリフォーム工事全体の費用の2分の1以上
- 住宅の引き渡し、または工事の完了から6カ月以内に自ら居住する
- リフォーム工事後の床面積が50㎡以上
- ローンの返済期間が10年以上
- その年の合計所得金額が2000万円以下
- 2025年12月31日までの入居
耐震改修をすると、条件によって税金の軽減や控除がある
改築工事と併せて耐震改修を行うのがコスト的にもオススメと前述しましたが、耐震改修で固定資産税の減額や所得税の控除が受けられる場合があります。
固定資産税の減額
耐震改修完了の翌年分の住宅にかかる床面積120㎡相当分までの固定資産税が、工事完了年の翌年度分1年間、2分の1に減額されます。現行の耐震基準に適合する改修であること、工事費用が50万円超であること、1982年1月1日以前からある住宅であることなどが要件。築40年を超える住宅で耐震改修を行う場合は、この制度の対象になるか税務署などに確認するといいでしょう。なお、制度期間は2024年3月31日までです。
所得税の控除
改築工事と耐震改修を同時に行うと、所得税が最大62.5万円控除(控除は納めた所得税が上限)されます。現行の耐震基準に適合する耐震改修であること、自ら居住する住宅であること、1981年5月31日以前に建築された住宅であることなどが要件。ただし、制度期間は2023年12月31日までです。
自治体の補助金制度なども調べてみよう
自治体によっては省エネリフォーム、バリアフリーリフォーム、耐震診断・耐震改修など、さまざまなリフォームを対象にした補助金制度が用意されています。改築工事の際に、省エネやバリアフリー、耐震に配慮したリフォームも行う予定なら、住んでいる自治体の制度を確認しておくのがおすすめです。

改築工事の依頼先選びのダンドリとポイントは?
複数の会社に見積もりを依頼する
改築工事をどこの会社に頼めばいいのか、普段、リフォーム会社や建築会社との付き合いがない人にとっては何から始めればいいのかわかりくいものです。まずは、どんなリフォーム会社、建築会社があるのか、広く情報収集することから始めましょう。
改築工事は規模が大きな工事になるケースが多いですから、依頼先候補としてリストアップするなら、増築や減築、間取り変更やリノベーションなど、構造部分にもかかわる規模のリフォームの経験が豊富な会社。その中から、気になる会社、好みに合う数社にしぼり、希望を伝えてラフプランと見積もりを依頼してみましょう。
見積もりが出たら金額だけで比較しないことが大切
複数の会社からラフプランと見積もりが上がってきたら、どのプランがいいのか、どの会社に頼むのがいいのかを検討します。
見積もりは金額が安い依頼先を選ぶためのものではありません。各社が提案するラフプランには自分が伝えた希望が反映されているか、リフォームのプロの視点からの提案は盛り込まれているかなど、プランの内容を比較してみましょう。金額も安ければおトク、というわけでもありません。
「家は財産で、消耗品ではないのでイニシャルコストで考えずにランニングコストで考えることが大切です。見積もり金額はちょっと高いけれど、その理由が住宅が長持ちするよう考えられた仕様になっている場合、トータルコストで考えれば見積もりが高くてもメリットがあるということです。その金額の中でどんな体制で仕事をするのか、どんな配慮があるのかといった数字の裏側にある物語を、自分のこれまでの人生の経験値から読み取っていくこと、自分の目で確かめることが大切ではないかと思います」
また、見積もりを依頼したり、プランの提案を受けたりする際のコミュニケーションを通して、その会社を知ることも大切。
「リフォームというのは新築と違い、不測の出来事も多く出てくるものです。実例や実績、職人さんの経験値、現場対応力、現場監督が現場につきっきりなのかといった現場の体制を知ることが大切です」
改築工事は建物の解体も含む規模の大きなリフォーム。ノウハウの豊富なリフォーム会社、建築会社と出会うためにも、早め会社探しをスタートし、慎重に比較検討するのがおすすめです。
●取材協力/一級建築士 佐川旭さん
構成・取材・文/田方みき
佐川旭建築研究所代表。一級建築士、インテリアプランナー。住宅だけでなく、国内外問わず公共建築や街づくりまで手がけている
広告制作プロダクション勤務後、フリーランスのコピーライターに。現在は主に、住宅ローンや税金など住宅にかかわるお金や、住まいづくりのノウハウについての取材、記事制作・書籍編集にたずさわる。

