
価格も立地も、魅力的な物件が多い中古マンション。
とはいえ、売るにしろ買うにしろ「何となく不安」があるのも事実。
そこで、考えられる不安要素をすべて払拭できるよう、不動産のプロである長嶋修さんに、中古マンションのあれこれを教えていただきました。
メリット、デメリット、注意すべき点を理解した上で賢くお得に中古マンションを売買しましょう。
2022年1月~12月に新規登録された(売り出された)中古マンションの平均築年数は28.16年 で、成約した中古マンションの平均築年数は23.33年。ここ10年の推移を見てみると、売り出された物件の築年数、成約した物件の築年数もどんどん上がってきていることがわかります。

中古マンション、特に築年数の古い物件の購入意向度が高まった理由を、さくら事務所の長嶋修さんに聞いてみました。複数の要因がありますが、主なものは以下の2つです。
このことから、低価格で流通量の多い中古マンションが魅力的な選択肢になっているようです。
「さらに、中古物件を購入してリフォームやリノベーションする人への融資が、ほとんどの金融機関で可能となっています。旧耐震マンションへの住宅ローンの制約も緩くなっている印象です。これに伴いリノベーション業者も増えてきて、中古マンション購入をさらに後押ししています」(長嶋さん)
物件が新耐震基準に適合していることを融資の条件としている住宅ローンは多くあります。しかし、【フラット35】のように、旧耐震物件であっても独自の耐震評価基準を設けているところも。
さらに、国土交通省が実施する住宅リフォームの支援制度なども、築古マンションの人気の一助となっています。
中古マンションの魅力は何といっても割安感。新築からどれぐらいたてばお買い得な価格になるのでしょうか?
「中古マンションの価格は一般的に、新築でなくなった瞬間から当初の建物価格の2割ほど安くなるといわれています。つまり、6000万円の新築マンションが、土地と建物の価格がそれぞれ3000万円だとすると、600万円安くなって5400万円になるイメージ。その後は徐々に値下がりし、築20年で下げ止まるといわれています。
首都圏、関西圏の都心部では、2018年あたりから『築5年以内の築浅マンションの価格が新築とほぼ変わらない』という状況が続き、近年では新築時より高い価格での成約事例も珍しくありません。新築マンションの供給が減ったことで、その分の需要が築浅中古に向かったようです。こういった特殊な事情で相場が変わることもあるので、市場の動向にも注目しておきたいですね」
「築20年で底値になる根拠ですが、あくまでも市場の平均値です。『20年たてば建物の価値がなくなって土地代だけになる』というわけではありません。不動産の評価は、土地代と建物代を合わせて『これくらいで売れるだろう』と価格がつけられます。その結果が平均して『20年で下げ止まっている』ということ。土地価格よりは高い金額になる場合がほとんどです」(長嶋さん)

マンションの価格を左右するのは次のような要因です。
それぞれについて説明していきましょう。
価格の下がりにくいマンションを買いたいのなら、立地を気にしてみましょう。中古マンションは好立地に建っていることが多いため、便利で資産価値の高い立地のマンションが手に入るかもしれません。
築年数が浅い築浅物件ほど価格が高い傾向にあります。これまで紹介してきたように、中古マンションは築20年で底値になり、その後は価格の下落がなだらかになります。
一般的に、広ければ広いほど価格は高くなります。ですが、エリアによっては、単身者のマンション購入ニーズが大きく、ファミリー向けの広い部屋は人気が少ないなどの特性があり、価格に影響を与えることもあります。
南向き、東向き、西向き、北向きの順に価格が下がっていきます。価格が低い西向きや北向きの部屋にもメリットはあり、生活スタイルによっては「西向きの部屋が一番良い」ということも。各方角のメリットを、こちらの記事で紹介しています。
立地や築年数などの条件が良くても、住人の方々が積極的に維持管理を行わなければ、住み心地や安全性が低くなり価格も落ちてしまいます。マンションの管理力も確認しておきましょう。
「同じ築20年でもその品質には大きなばらつきがあります。品質を決める要因は、個別のマンションが持つ『管理力』です。
例えば『管理費は適切か』とか『修繕積立金は十分か』といったことについては、所有者で構成するマンション管理組合で精査し、必要に応じたアクションを起こす必要があるのです。
昨今では『マンション管理は管理会社がやってくれるもの』と思っている人も少なくなりましたが、それでもまだ主体的にマンション管理にコミットする所有者が多いわけではありません。管理組合の活動状況について、あらかじめ調べておきたいところですよね」
賃貸や一戸建て暮らしからマンション購入を考えている方は、「管理力」といわれてもイメージしにくいかもしれません。「長く住める中古マンション選びのポイント」のコーナーで、マンションに必要な管理を詳しく紹介しています。

中古マンションは価格が大きな魅力ではありますが、安く買えても長く住めないようでは元も子もありません。「鉄筋コンクリートの寿命は100年」とも聞きます。例えば築20年のマンションを買った場合、あと何年住み続けられるのでしょうか?
老朽化したマンションは、建て替えによって安全性や資産価値を向上させることができます。”マンションの建設完了→取り壊し→建て替えたマンションが建設完了”するまでの平均期間は40.3年というデータがあります(2022年 東京カンテイ )。2014年の同様の調査では33.4年でしたので、この期間は徐々に延びていっています。
「では、マンションは築40年で寿命がきて、建て替えが必要になるの?」というと、そうでもありません。建て替えられたマンションの中には、まだまだ住み続けられるけれど資産価値向上のために建て替えたものが含まれていますし、今でも活用されているマンション(建て替え不要のマンション)は含まれていません。
「それはあくまでも『すでに壊されたり建て替えられたマンションの平均築年数』。人間で考えると、元気に生き残った人が計算されていない平均寿命ということになります。それは本当の平均寿命ではありませんよね」(長嶋さん)
「実際に、築40年以上たっても活躍しているマンションはたくさんありますし、国土交通省でも『鉄筋コンクリート造の物理的寿命は117年と推定』すると発表しています(2013年 国土交通省「RC造(コンクリート)の寿命に係る既往の研究例」 )。人によっては、120年、150年もつという人もいます。もちろんそれは、工事に手抜かりがなく、欠陥もなく、点検や管理がきちんと行われていて初めて得られる寿命。その場合は最低でも100年もつといわれています」(長嶋さん)
日本国内でマンションが本格的に供給され始めたのは戦後です。ヨーロッパのように、築100年を超えるようなマンションが現役で使われている実績はまだありません。日本のマンションの本当の寿命がわかるのはこれからです。
財務省が発表している、減価償却資産の耐用年数等に関する省令によると、マンション(鉄筋コンクリート造の住宅用の建物)の耐用年数は47年。ですが、耐用年数とはあくまで減価償却の計算に使われる数字です。マンションの寿命を示すものではありません。

国土交通省によると 、2022年現在、築40年超のマンションが約125.7万戸存在し、10年後には約2.1倍、20年後には約3.5倍の約445.0万戸と急増していくそうです。そのため、「マンションストック長寿命化等モデル事業」という、マンションの寿命を長くする取り組みの支援を進めてきました。適正な維持管理や、長寿命化のための改修や建替えを、国を挙げて促していこうとするものです。
それ以前から、「住宅ストック化活用型社会」=「いい家を建てて長く住み続けよう」という動きがすでに始まっています。国の後押しを受けることで、マンションの寿命は今後さらに長くなっていきそうです。
「もともとコンクリートという素材は、新築のときが一番弱く、50年かけてゆっくり強くなり、また50年かけて弱くなっていく、という性質を持っています。つまり、コンクリート自体は50年後が一番強い状態だということ。また、例えばマンションのタイルの上にコーティングを施すことで、寿命をさらに60年延ばす、といった新しい技術や工法が次々と生まれています。今すでに築年数がたったマンションでも、こういった技術で寿命を延ばしていける可能性がある、ということです」(長嶋さん)

100年もつといわれる鉄筋コンクリート造なのに、40年ほどで廃墟のようになっているビルやマンションも存在します。「ホントにそんなに長持ちする?」と不安になる気持ちも……。長寿命のマンションと、そうでないマンションの違いはどこにあるのでしょうか?
「築年数以上に寿命に大きな影響を与えるのが、『どんな管理が行われているか』。例えば、建てた後そのまま放置していると、どんなに頑丈な鉄筋コンクリート造の建物でも、50年でボロボロになってしまいます。マンションは、管理組合がしっかり運営されていて、修繕計画が予定通り行われているかどうかで、寿命が大きく違ってくるのです。中古マンションを購入するときは、『修繕積立金がきちんと貯まっているか』『修繕計画が適切に予定され、実際に行われているか』『何かあったときにこまめに修繕されているか』を確認しておきましょう。管理組合が保管している議事録を見れば把握できるはずです」(長嶋さん)
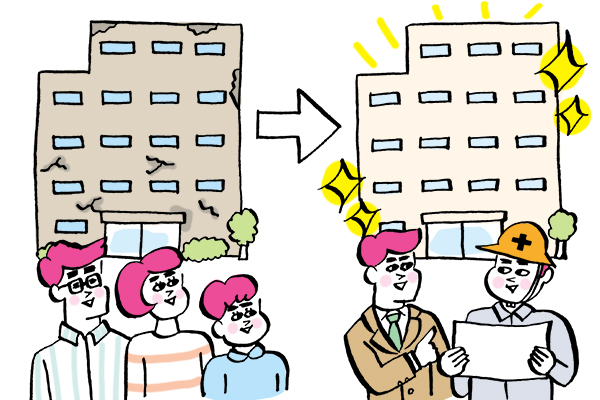
「アメリカでは、マンション管理にかかわるあらゆる書類を見せてもらい、『納得した』というサインをした上で中古マンションを購入します。しかし残念ながら日本では、所有者以外への議事録の開示は義務付けされていません。開示しているのは、ごくごく少数派。『見せてほしい』といっても渋られるケースがほとんどです。そういうときは『修繕積立金の額』で判断しましょう」(長嶋さん)
『マンションの修繕積立金に関するガイドライン(国土交通省)』によると、修繕積立金の適正な金額は、m2当たり200円といわれます。この金額がしっかり集められていれば、15年ごとの大規模修繕時にお金が不足する可能性は低く、マンションの寿命を守ることができます。
適切な修繕積立金の目安 m2あたり200円(月額)
(例)専有面積70m2のマンションの場合 70m2 × 200円 = 1万4000円(月額)
例えば、このマンションの修繕積立金が1万円になっていると、毎月4000円のマイナスになり、15年間では一戸当たり72万円が不足することになります。100戸のマンションなら7200万円の不足。「お金がないからきちんと修繕できない=寿命を守れない」可能性がでてきます。もちろん、物価の上がり下がりの影響を受けることも考えておきましょう。
「新築時には少しでも買い手が付きやすいように、修繕積立金を低めに設定して販売するマンションもあります。その場合は修繕工事の際に不足分を追加で徴収されることになります。ホームページをつくって情報を公開しているマンションなども出てきているので、そういったマンションなら安心ですね」(長嶋さん)
内見時に、管理の良し悪しを確認する方法はないでしょうか。
「いきなり部屋に入らないで、外まわりから見ていきましょう。タイルが剥がれたり浮いたりしているのに放置しているマンションは要注意。築10年を過ぎると、3~5%のタイルはそのような状態になってくるものも多いです。管理人に『これはいつ修繕される予定ですか』と聞いてみてもいいかもしれません。また、そもそもエントランスが散らかっているようなマンションは問題外。何年も前の掲示物がそのままになっていたり、駐輪場が整頓されていなかったりすれば、推して知るべしです。管理状態が適正かどうかわかりにくいときは、私たちのようなホームインスペクターに頼ってみることもオススメします」(長嶋さん)
管理状況や修繕計画をチェックするときに、特によく見た方が良い項目を、長嶋さんに教えていただきました。
「一番大きな問題は『配管』です。1970年代に建てられた築50年超のマンションは、排水管が下の階の天井裏を通っているケースが多く見られます。排水管を交換・移設しようとすると、下の部屋の方に協力してもらう必要が出てきます。下の部屋の天井をはがして、排水管を取り替えさせてもらうのは、実際にはかなり厳しいです。その場合は、自分の住戸の床を一段高くして、その中に新しく給水管を設置するケースが多いようです。もちろん、そうなると天井高は低くなります。また、床のコンクリートに配管が埋め込まれている場合は、コンクリートをはがして交換することになります。その場合は、配管の寿命がマンションの寿命になりかねません。竣工時にどんな工事が行われていて、どのように修繕されてきたかは知っておきたいですね」(長嶋さん)
配管のメンテナンスができるかどうかで、マンションの寿命が大きく違ってくるようです。配管に限らず、マンションが建てられた年代によって主流の施工方法が違うため、チェックしておきたい点は異なります。下の年代別チェックリストも参考にしてみてください。
〇時代背景と特徴
・新耐震基準施工前
〇注意すべき点
・耐震改修や補強工事などがなされているか
・エアコンのスリーブがあるか
・給排水管はどこにあるか
・音の伝わりやすさに問題はないか
・スラブ厚はどれくらいあるか(13~15cm程が中心)
〇時代背景と特徴
・1981新耐震基準制定
・バブル経済を背景にした投資用マンションが登場
・リノベーションしやすくなる
〇注意すべき点
・給排水管はどこにあるか
・断熱材などが使われた物件かどうか
・音の伝わりやすさに問題はないか
・壁や床が薄い、修繕積立金や管理費等の設定が極端に低いなど、この時代の投資、投機用マンションに多い問題点がないか
〇時代背景と特徴
・アウトフレーム工法が登場
・1999年「住宅品質確保促進法」制定、「住宅性能表示制度」スタート
・バリアフリー仕様が増える
・耐震技術が発達
〇注意すべき点
・部屋数を確保するために、一部屋が小さくなっていないか
・天井高に不足がないか(階高がまだ2700~2800mm程が中心)
・スラブ厚はどれくらいあるか(二重床、二重天井になっているか)
・アウトフレーム工法、制振や免震構造が採用されているか
〇時代背景と特徴
・2003年建築基準法改正
・大規模開発・超高層タワーマンションが増える
・ボイドスラブの普及
〇注意すべき点
・梁で囲まれた面積が大きくなるボイドスラブで振動が大きくなり、音が響きやすくなっていないか
・スラブ厚はどれくらいあるか(18~20cm程が中心)
・配管が鉄管から樹脂管に、給湯管は銅管になっているか
マンションの寿命を左右するのは、建物の品質や管理以外だけではありません。管理を行うのはマンションの住人ですから、どのような人が住んでいるのかも大切なポイントです。
「どんな人が住んでいるか、住んでいないか、ですね。土地や建物を所有する人が亡くなって、相続時に登記されないまま空室になり放置されるとどうなるでしょう?まず、管理費や修繕積立金が徴収できなくなります。そして、管理が不十分になって劣化が進んだり、管理組合が運営されにくくなる、といった問題が出てきます。居住者の年齢層が高くなるほど、この問題も発生しやすくなります。管理費や修繕積立金はきちんと払われるとしても、例えば今70歳の人が大規模な修理や建替えが必要になったときに、新たに大金を出したいと思うでしょうか?定期的に若年層が入ってきて居住者が入れ替わるような、駅近の人気物件ならあまり心配はないかもしれませんが、郊外のバス便マンションなどでは特にこういった問題が起こりやすくなります。マンションは共同住宅です。自分の部屋だけ長生きさせることはできないのです」(長嶋さん)

耐震基準とは、建築物が最低限度の耐震能力を持っていることを保証する基準のことで、建築基準法によって定められているもので、大幅な改正が行われたのが1981年6月。建築業界などではこの改正以前の基準を「旧耐震基準」、以降の基準を「新耐震基準」と呼んで区別しています。
建築確認日が1981(昭和56)年6月1日より前の物件は旧耐震基準、それより後の物件は新耐震基準で建てられています。違いとして、旧耐震基準では「震度5強程度で倒壊や崩壊が起こらなければ良い」とされており、新耐震基準では「震度5強程度の地震ではほとんど損傷が起こらず、震度6強から震度7程度でも命に危険を及ぼすような倒壊などの被害が起きない」とされています。
旧耐震基準の中にも新耐震基準のマンション以上に丈夫に建てられたマンションもありますが、新耐震基準のマンションであれば、基本的な耐震性が高く設定されているという安心感があります。
新築マンションに比べて、「お金を借りにくい」「手続きが煩雑」などといった問題はあるでしょうか?
「昔と違って、今は『中古マンションだからローンを利用しにくい』といった問題は全くありません。問題は、新築か中古か、ということではなく、エリアや広さです。中古マンションに限らず、例えば『水害の可能性が高いエリアに建つマンションには貸出期間を短くしたり、金利を高くする』といった、個体ごとの差別化が今後はもっと進みます。水害の可能性が高いと損害保険の掛け金が2~3倍になったりするので、そこも気をつけておきたいですね」(長嶋さん)
担保となる物件の良し悪しについて見極めが必要なのは、新築マンションも中古マンションも同じ。マンション代とリフォーム代を一本化できるようになったこともあり、ローンを利用する上では中古マンションだからといって不利な点はなさそうですね。
住宅ローンを組んで中古マンションを購入すると、年末のローン残高に応じた控除額が、10年間にわたって所得税から控除されます。1年当たりの 控除額はローン残高の0.7%で、残高の上限は、長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅の場合3000万円で、その他の場合は2000万円。前者の場合は最大21万円、後者の場合は最大14万円の控除が受けられます。これが入居の年から10年間にわたって続くという、マイホーム購入者にとってとてもうれしい制度です。しかし、同じように住宅ローンを利用していても、購入する物件によっては控除されない場合があります。後から知ってがっかりしないように、購入時には以下の要件に当てはまるかどうか、確認しておきましょう。
専有面積50m2以上(そのうち1/2以上を自分で居住するために用いること)
1982年(昭和57年)以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)
住宅ローン控除について詳しくはこちら
中古住宅でも住宅ローン控除は受けられる!適用条件や書類などのポイント・注意点を解説
リノベーション物件以外は、何かと修繕が必要になるイメージのある中古マンション。解体してみないとわからない部分もありますが、「リフォーム代にどれくらいかかるか」は、購入前に把握しておきたいものです。
リフォーム代の目安はこちらから
中古マンション/中古一戸建て×リフォーム リフォームの費用相場と築年数別の目安額
また、入居時には使えた設備、例えば給湯器のような設備の寿命が入居後数年でくる可能性もあります。後から思いがけない費用が発生して家計に支障が出ることのないよう、資金計画にはゆとりを持っておきましょう。
さらに、マンションの修繕工事費用が足りないときには、区分所有者全員から追加の費用として数十万~数百万円の費用が徴収されることがあります。その際には居住年数は考慮されないので、「工事がいつ行われたか」「修繕積立金は十分用意されているか」について確認しておきましょう。
買う時には安くしてほしいけれど、売る時には少しでも高くしたいもの。売主個人として何かできることはあるでしょうか?
「見た目の印象はとても大事です。居住中に内見してもらう場合、例えばアメリカでは要らない荷物はトランクルームに預けるなどして見映え良くする努力をします。商品として売り出すための演出を『ホームステージング』といいます。日本でも、プロによるインテリアコーディネートを行った上で売り出す仲介会社もあります。実際に、40万円の費用をかけてきれいにした結果、売値が300万円上がったケースもあります。生活感のあるものは隠して、おしゃれな絵画や照明器具をそろえたり、印象を左右する水まわりだけでもプロに頼んでピカピカにしてもらったり。費用対効果を考えた上で、工夫してみてはどうでしょうか」(長嶋さん)

平均的に築20年で底値になるので、安く買うなら築20年超物件が狙い目
マンションの寿命は本来100年超。ただし、本来の品質以上に管理が左右する
住宅ローンは利用しやすくなったが、ローン控除は使えない場合がある
買うなら管理と住人を見て、売るなら見映えを良くして
